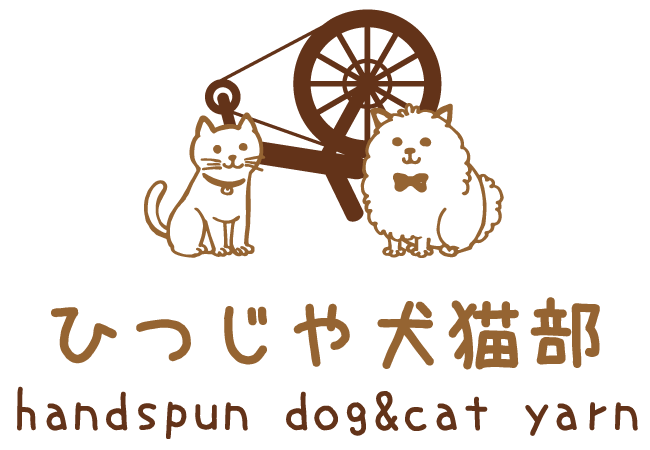犬や猫の毛は毛糸に紡ぐことができます
春の抜け替わりの時期、また毎日のブラッシングで抜けた犬猫の毛を見て、「…もったいないなあ」と思われたことはありませんか? 実は、犬猫の毛も立派な毛糸になるのです。
お客さまから犬猫の毛を提供していただき、なにを作るのか、また用途によってはどれくらい羊毛を混ぜるかをご相談させていただき、毛糸を紡ぎます。
※皮膚病・感染症・伝染病のおそれのある犬猫の毛はお預かりできません。(うちにも家族の一員として溺愛している犬猫がおります。どうかご理解くださいませ) ※完全オーダーメイドのため、作業着手後のキャンセルは受け付けられません。 ※すべての犬猫の毛が毛糸にできるわけではありません。毛が短い、フェルト化して固まっている等様々な理由でご注文をお引き受けできない場合もあります。どうかご了承ください。
過去に作成した犬猫糸
ひつじや 犬糸猫糸ギャラリーに犬種猫種ごとに掲載しております。
犬糸猫糸が出来上がるまで
1.毛を集める
 ブラッシングやシャンプーのときなどに抜けたもののみにしてください。(床に落ちている毛はゴミやホコリが混入しているので混ぜないでください)
毛に絡んでいる夾雑物(草木の欠片など)はできるだけ取り除いていただけると毛糸の仕上がりが良くなります。
ブラッシングやシャンプーのときなどに抜けたもののみにしてください。(床に落ちている毛はゴミやホコリが混入しているので混ぜないでください)
毛に絡んでいる夾雑物(草木の欠片など)はできるだけ取り除いていただけると毛糸の仕上がりが良くなります。
色を分けて毛糸にしたい場合は、色ごとに袋を分けて保存してください。ひつじやでは色分け等の作業は行いません。
カット毛の場合、ご注文はお引受できません。(短い毛くずのせいか、作業者のくしゃみ肌の痒みがひどく起こるようになってしまいました)抜け毛のみお引受しております。
2.用途を決める
毛質にもよりますが、肌の弱い部分(首まわりなど)にはあまりオススメできません。 生えているときは一方方向なのでさほどチクチクしないのですが、紡ぐと毛が四方八方を向いてしまうせいか、格段にチクチク率が上がります。
3.羊毛を混ぜるかどうか、また混ぜる場合は割合を決める
これは用途によります。犬猫毛100%でもできないことはありませんが、かなり硬くて弱い毛糸になります。(毛同士の絡み合う力が弱いため、羊毛の毛糸よりも撚りをきつく入れないと毛糸にならないのです。撚りをきつくする=硬い毛糸になります) 若干羊毛を混ぜたほうが、毛糸としての風合いも良くなり、耐久力もアップします。
どうしても首まわりに使いたい、ということであればメリノ種、セーターなどにするのであればコリデール種など。毛の太さ硬さに合わせて羊の毛も使い分けます。
4.羊毛を混ぜる、また紡ぎやすいよう毛をほぐす
 ブレンド率に従って、犬猫毛に羊毛を混ぜます。
まずは手で細かく分けて混ぜ合わせ、更にハンドカーダーという器具を使って丁寧に混ぜ込みます。
偏りのないよう、とにかく混ぜて混ぜて混ぜて混ぜて、シート状にします。
ブレンド率に従って、犬猫毛に羊毛を混ぜます。
まずは手で細かく分けて混ぜ合わせ、更にハンドカーダーという器具を使って丁寧に混ぜ込みます。
偏りのないよう、とにかく混ぜて混ぜて混ぜて混ぜて、シート状にします。
羊毛を混ぜない場合も、紡ぎやすいよう毛を柔らかくほぐし、繊維が同じ方向を向くようカードします。
5.紡毛機で紡ぐ
 ニットにするのであれば甘め、織るのであればキツめに紡ぎます。しかし羊の毛と違い犬猫毛は抜けやすいので、ニット用であっても若干キツめに撚りをかけています。
ニットにするのであれば甘め、織るのであればキツめに紡ぎます。しかし羊の毛と違い犬猫毛は抜けやすいので、ニット用であっても若干キツめに撚りをかけています。
6.撚り止めをし、洗う
出来た糸を蒸します。これで撚った状態で毛糸が安定します。
撚り止めした糸をカセ上げ(大きな輪状に巻く)します。ネリモノゲンという洗剤を溶かしたぬるま湯に沈め、液が冷めたら脱水、すすいで脱水。陰干しにします。
7.玉に巻く
毛糸が完全に乾いたら、カセがくずれないように気をつけながら、玉に巻きます。
出来上がり
 毛糸玉の出来上がりです。この状態で納品いたします。
毛糸玉の出来上がりです。この状態で納品いたします。
この後、織ったり編んだり、お好きなものをおつくりください。 【ひつじや犬糸猫糸ギャラリー】へ